中小企業で執行役員をしていた私ですが、少し前に転職しました。40代後半の転職も珍しくはない時代ですが、簡単じゃない、という話も多く聞きます。
私がいざ転職しようと思った時、ネット上ではITやスタートアップではない会社で執行役員をしている人の転職話があまりなくて。会社の数に近い人数いるはずの執行役員の皆さんがどうしているのか気になったのですが、うまく見つけられませんでした。
そのような訳で同じような立場の方にむけて記録を残そうと思います。どなたかのお役に立てばうれしいです。
執行役員が転職を考えたら、まず確認したいこと
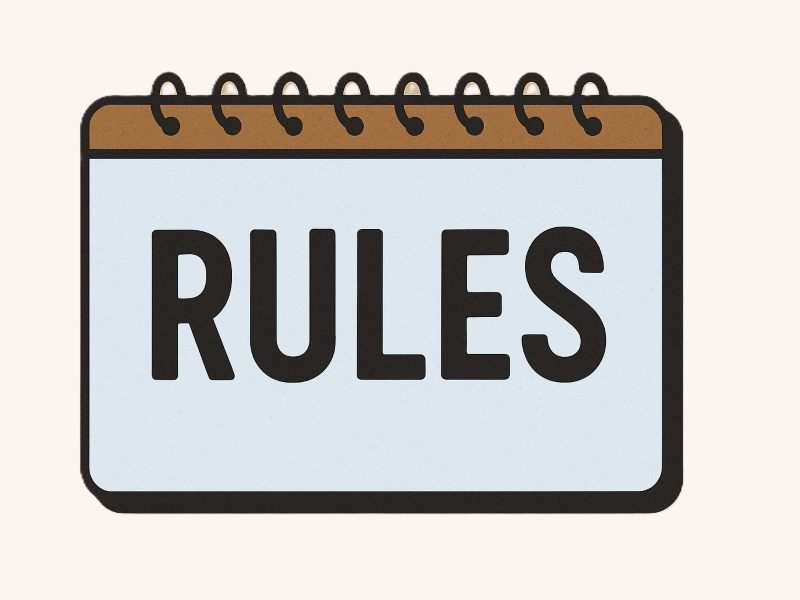
まず始めに確認が必要なことは、あなたがどのタイプの執行役員なのか、ということ。具体的には2タイプあります。
- 委任型の執行役員:委任契約を結んだ形の執行役員。契約なので期間が決められている。従業員でないので、給料ではなく報酬。
- 従業員型の執行役員:従業員の立場のまま。従業員のままなので、従来通り給与をもらう。
委任型は専門性の高い方と契約を結ぶ感じ、授業員型は社員の最高位に昇進する、というイメージです。
退職を考えた時に、委任型は契約書で期日や契約の破棄についての記載があるはずですので、それに従うことが基本となります。ちょうど任期が終わるのであれば退任の申し入れをして更新しない、任期途中の場合はどうするか、決められていなければ双方協議、といったところでしょうか。
一方、雇用型の場合は基本として「従業員」ですから、法律上は正社員の場合2週間前までに提出でOK。ただ、通常は就業規則があって30日前、などと決められているので、基本は就業規則に従います。
就業規則通りに退職届けを出せばよい、というわけでもなかった
実際に執行役員が退職する時に【従業員型だから】という理由で、就業規則通りに他の社員同様の退職届け提出のタイミングだとトラブルの元になるかもしれません。
就業規則って、新入社員だから、とか課長だから、部長だからと細かく規定が分かれていませんよね。分かれていても諸手当くらいでしょうか。そして、執行役員になっているということは、社内で負っている責任が多い、ということでもあります。新入社員さんなら例えば30日前で退職しても大きな影響はないと思いますが、執行役員ともなると色々弊害も出てきます。
一方、あくまでも法律上は2週間前でよいわけですし、就業規則上も30日前でよいわけです。
このあたりをどう判断するかは、自分がどのように退職したいのか、に関わってくると思います。
色々と理由があってできるだけ早く辞めたい、多少揉めても早く辞めたい、なるべく穏便に辞めたい、など、自分が【どのように退職したいか】を考え、引き継ぎの期間などを考えるとおおよその退職時期が出てくると思います。
執行役員は3ヶ月より前に退職を申し出るのが良さそう

では、いつ退職を知らせるのが正解か?
こればかりは前述の通り会社により、人により、どう辞めたいかによるのですが。結論としては3ヶ月から6ヶ月の間くらいが良さそうです。
私自身は3カ月前に社長に伝えました。私の上には社長だけだったのですが、副社長とか専務とか常務がいる場合は、すぐ上の上司に伝えるのが一般的です。
3カ月前に伝えようと思った理由は3つ。
- 引継ぎ期間は2ヶ月と試算した
- 有休代休が合わせて40日あったので、1ヶ月休もうと思った
- あまり早く伝えるとグズグズされそうなので、短期決戦の方が良いと思った
結果、この読みは甘かったです。実際どうなったかと言うと、
- 引き留めにあい、退職を認めてもらうまでに1ヶ月かかった
- 後任を決めずグズグズされ、引継ぎがなかなかできなかった
- 結局、有休は6日しか消化できなかった
有休は2週間はとると決めて引き継ぎを計画して進めていたものの、退職前のタイミングで体調を崩して出勤できなくなってしまいまして。病気なら休めるかというとそうでもなく。結局、在宅勤務になり、体調が戻ってから出社できなかった分は出社したので、何だかんだと働くハメに。なお、有休は買い取ってくれませんでした。
転職先には内定時に早く来て欲しいと言われて、2か月後入社のオファーでした。退職をなかなか認められないこともあり、入社日を3ヶ月後に伸ばしてもらったのですが、私の場合は4ヶ月は必要だったのかもしれません。ただ、前職の体質を考えると4ヶ月にしたところで同じようなことになっていたような気もします。
いずれにしても、退職時期は明確に意思表示して、なし崩しは避けなければなりません。有休消化など色々と譲歩はしましたが、退職時期だけは最初から最後までブレさせずに妥協しない姿勢で交渉しました。
6ヶ月前に伝えた執行役員の友人のケース
私より規模の大きい中小企業で執行役員をしていた友人がいます。
彼の場合、6ヶ月前に信頼できる自分の周りに退職の意志を伝え、引継ぎ体制を密かに作っておいたそうです。その後、上長に伝え、引き留めにあうも振り切り、有休はフルに消化して退職したとのこと。
少し間を開けてから転職したので、有休も使い切ることができたようです。
私が退職を上司に伝えた時、社長は「6ヶ月は引継ぎに必要」と言いましたが、私の実感としては6ヶ月は長すぎると思います。前職の関係でお世話になった社労士の先生も「6ヶ月は長い」という見解でしたので、3ヶ月〜どんなに長くても6ヶ月が妥当なラインなのかと思います。
「引き継ぎ」とは何か?間に合わない時はどうなる?
引き継ぎの期間をどれだけ用意しても、「間に合わないのでは?」と思う瞬間はやってきます。私は会社の中で複数の役割を果たしていたのと、後任がなかなか決まらなかったため、間に合わないかもしれない、と思うことは多々ありました。
そんな時に、考えたのは「引き継ぎとは何か?」。そして「何を引き継ぐのか?」を自分の中で決めておくことが大事です。実際に社長からは、私のやり方を1から10まで後任に教えておくように、と言われました。メールの書き方ひとつ、全て見せて教えて真似できるようにしておいて欲しい、というリクエストです。
これに対してはNoを明確に伝えました。というのも、引き継いだ仕事をどうやっていくのかは、後任の裁量だと思うからです。業務を行う上に必要な情報はしっかり伝えますが、どう進めていくか、どういう関係性を構築していくかは営業それぞれの得意分野やスタイルがあります。
私の仕事の仕方をコピーしてもらうのは1種のマイクロマネジメントですし、その方法では後任が自分で成果を出せるようにはなりません。
退職することで、少なからず会社に迷惑をかけてしまう、という後ろめたさがあるので、言われたようにしそうになりますが、私はこの部分を間違えないように、自分で線を引いていました。私のコピーを作るのには時間がいくらあっても足りません。
しっかりと何を引継ぐのかを決めていても、時間が足りなかったらどうなるか?その対策は2つ。
- 引き継ぎ資料をきちんと作っておくこと
- 資料、データのありかを明確にしておくこと
極論、これができていれば引き継ぎの責任を果たしていると考えます。これは引き継ぎ相手がいなくてもできるので、コツコツ進めておきましょう。
最終的に引き継ぎ相手が決まらなかったら、引き継ぐ先は「上司」です。これって意外と盲点だと思うのですが、上司は私の仕事の管理責任があるのですから、上司に引き継げばよいのです。自分が社長でない限り、必ず引き継ぐ人はいるのです。
執行役員の退職で大事なのは、自分がどういう立場の執行役員かを確認することと、どういう退職をしたいのかを明確にすること。そうすると、自ずと退職を会社に申し出る時期がハッキリするはず。私の経験上の目安は3~6ヶ月前です。
もうひとつ、退職時期を大きく左右する引き継ぎは、何を引き継ぐかを明確にして、割り切ることがポイントです。人や立場によって「引き継ぎ」に求めるものが違うので、明確化しておき、解像度をすり合わせていくことも大事だと思います。



コメント